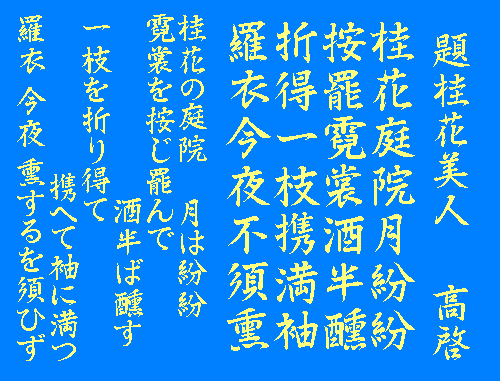
解説は画像の上で左クリックすると出ます
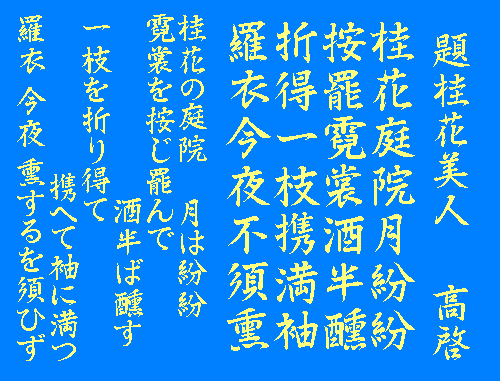
桂花庭院月紛紛 桂花の庭院 月は紛紛
按罷霓裳酒半醺 霓裳を按じ罷んで 酒半ば醺す
折得一枝携満袖 一枝を折り得て 携へて袖に満つ
羅衣今夜不須熏 羅衣 今夜 熏するを須(もち)ひず
<通釈と解説>
10月になると、毎年この季節には金木犀(桂花)の香りが街に満ち、私は1年でも最も幸せな時節を迎えます。口の悪い連中は「芳香剤の臭いだ」などと言って私をからかいますが、朝まだきのひと時、夕暮れの誰そ彼の時、月の皎々と照らす夜、いつでもこの香りに出会うと心の奥深くまで澄み渡るような気がします。
今月は、金木犀の香りを詠った高啓の詩を読みましょう。
[口語訳]
金木犀の花が香り咲く庭には月の光があふれかえり
美女が踊りを終えればちょうど酒も良いころあい
一枝折って袖に入れれば
今夜は薄衣に香を焚くまでもない
以前、みつはしちかこさんの「チッチとサリー」という漫画にこんな場面があったように覚えています。
デートの待ち合わせの前に金木犀の木陰にしばらく隠れていて、「頃や良し」と出ていけばどんな香水よりも素敵な香りが服に染み込んでいる。二人とも幸せな気分に浸っていく。
私の文章力ではみつはしさんのあの穏やかな雰囲気を表現できないのでもどかしいのですが、自然の花や木が与えてくれる香りは、本当に胸の中を清らかにしてくれますね。
漢詩では、桂花と月は切っても切れない関係です(月には桂の大木があると言われてます)。高啓のこの詩は、描かれた絵を見て作られたものでしょうが、更に美人を配して、まばゆいような絵だったことでしょう。
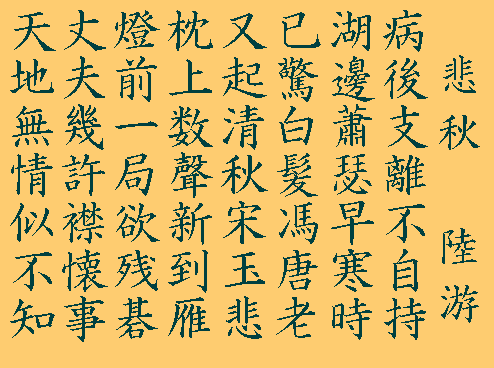
病後支離不自持 病後 支離 自ら持せず
湖邊蕭瑟早寒時 湖辺 蕭瑟 早寒の時
已驚白髪馮唐老 已に驚く 白髪 馮唐の老
又起清秋宋玉悲 又た起こす 清秋 宋玉の悲しみ
枕上数聲新到雁 枕上 数声 新たに到りし雁
燈前一局欲残碁 灯前 一局 残らんと欲する碁
丈夫幾許襟懐事 丈夫 幾許ぞ 襟懐の事
天地無情似不知 天地無情 知らざるに似たり
<通釈と解説>
もう少し早い時季の方がこの詩には合ったかもしれません。ついこの間も陸游の詩を推薦したばかりなので迷ったのですが、でも何ともこの詩を紹介したくて選びました。
南宋の陸游、六十歳の折の詩と言われます。
[口語訳]
病後のこの身体はボロボロで自分でも支えきれず
湖のほとりはものさみしい早寒の季節だ。
私の髪がすでに馮唐の如く老いたのを驚き
秋の気配は私に宋玉のような悲しみをもたらす。
枕辺には北からの雁の声がいくつか
灯の前には放り出されたままの碁盤。
男子の胸の内はどれほどの深さか
だが、天地は無情、一向に知らぬげである。
「馮唐」は、漢の武帝の代、年老いて(九十歳)から高官の資格を得たが老体のために仕官できなかったという不遇の人物、また、「宋玉」は戦国時代の楚の国の人、屈原の弟子とも言われていますが、『楚辞』で秋を悲しみの季節として詠った人物と言われます。
そうした故事をいれて自身と季節の寂寥感を詠いながらも、実はこの詩の主眼は頸聯の第五句・第六句にあります。
南宋の詩人にとって北からの使者、「雁」は、「金」によって占領、抑圧された北の祖国からの便りに他なりません。
そして、途中で投げやられたままの碁盤、戦いを放棄して為す術もない政局。
この二句によって、詩人の悲しみが憂国と季節の移ろいとの相乗によるものだと分かります。
時の政治への絶望と無力感、愚かな指導者の下で国が滅んでいくのを眺める国民の悲しみ、いよいよ季節は晩秋の深み、せめて憤りだけでも陸游に負けずに持ち続けたいと思います。
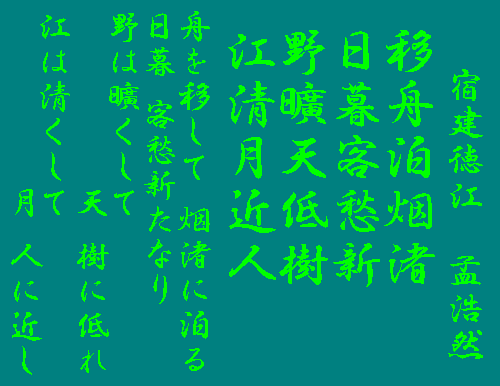
移舟泊烟渚 舟を移して 烟渚に泊る
日暮客愁新 日暮 客愁新たなり
野曠天低樹 野は曠くして 天 樹に低(た)れ
江清月近人 江は清くして 月 人に近し
<通釈と解説>
朝晩の冷え込みが急にやって来て、つい油断をした私は風邪をひいてしまったらしく、ここ数日、頭が重かったり、食欲が無かったりと、困っています。
今年は7月8月と病院暮らしだったので、夏の暑さを味わうことなく秋に入ってしまいました。残暑が厳しかったとは言え、やはり季節を一つパスして来てしまったツケでしょうか、冬に備える身体の準備が整っていないようです。
四季それぞれを経ることがやはり大切なのでしょうね。冬の寒さを耐えてくるからこそ春の花も美しく咲くし、夏の暑さを乗り越えて来るからこそ秋の果物や穀物も美味しく実る筈です。というわけですから、この冬の寒さも嫌がらず、この季節なりの味わいを探しましょう。えっ、冬を好きな人が多いのですか?これは失礼しました。
漢詩の世界でも冬を詠んだ名詩はいくつもありますが、さて、今年の立冬は盛唐の孟浩然、「宿建徳江」を『唐詩三百首』から読みましょう。
[口語訳]
舟を漕いで行って夕霧の渚に停泊すると、
日暮れのためか旅の愁いがいよいよ新たになる。
原野は広く、空は樹木の上に垂れるようで
江水は清く、水に映る月は手に届くほどに近くだ。
起句に「地」、承句に「時」、転句に「岸」、そして結句に「水」を詠じているのだというのが古来の注釈だそうですが、そんなに改まって言われなくても分かりますよね。それよりも、清の沈徳潜が言う「下半写景而客愁自見」(後半は叙景であるが、自然に客愁が現れてくる)という言葉がよく詩を表していますね。
後半の対句で、広々とした光景を描き、故郷とつながる「月」がすぐ手元に見えると言ってますが、だからこそ、一層故郷の遠さを暗示する、つまり客愁が深まるわけで、景から情を浮かばせるしみじみとした詩だと思います。
孟浩然の「自然詩人」の面目躍如といった作品ではないでしょうか。
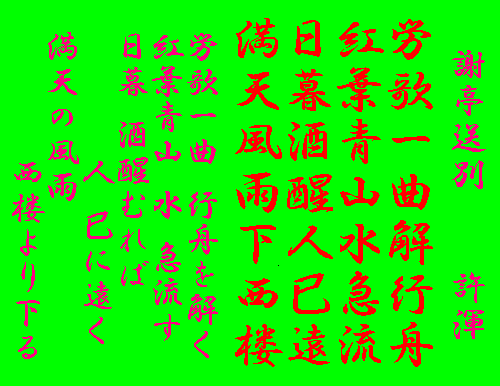
労歌一曲解行舟 労歌一曲 行舟を解く
紅葉青山水急流 紅葉青山 水 急流す
日暮酒醒人已遠 日暮 酒醒むれば 人 已に遠く
満天風雨下西楼 満天の風雨 西楼より下る
<通釈と解説>
この23日、南木曽の昼神温泉に出かけました。温泉療養が名目ですが、一番の期待は紅葉を見たかったのです。
今年は体調不良もあり、あまり出歩いていませんので、季節の移り変わりに鈍くなっています。時季が早いのか遅いのかも分からないまま、妻に運転してもらって中央高速を走っていきました。
名古屋を抜けた辺りではまだ早いくらいでしたが、標高が上がるにつれて山々の彩りが深くなり、少しずつ季節を渡って行くような感覚、晩秋から冬を一気に抜けきったような思いでした。
さて、今季の推薦詩は、晩唐の詩人 許渾 の『謝亭送別』です。
[口語訳]
別れの曲とともに、旅行く舟はともづなを解いて出発する。
紅くもみぢした樹々、緑の山々、水の流れは速い。
日暮れ、酒の酔いから醒めれば、旅人である友はすでに遠く去り
遙か一面、風は吹き渡り雨は降る中、私は西の楼から下りて行く。
「労歌」は、送別に際にうたう歌、かつて金陵(現南京)の南郊外にあった送別の地、「労労亭」でうたわれた歌なので、この名があるそうです。
前半の晴天の景色、紅葉と青山の鮮やかな色彩の対比の景から、後半の満天の風雨という暗い陰惨な景へと時間を流しながら移っていく構成は、スケールが大きく、別れの情を一層強く引き立たせていますね。
別れの悲しみに打ちひしがれた詩人が、夕暮れ、雨と風の中で濡れながら、楼をトボトボと下りて行く姿がくっきりと目に浮かぶようです。
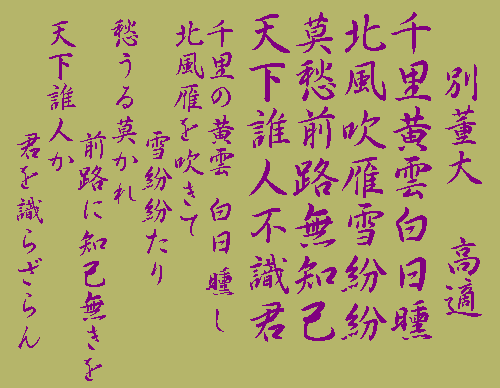
千里黄雲白日![]() 千里の黄雲 白日
千里の黄雲 白日![]() し
し
北風吹雁雪紛紛 北風雁を吹きて 雪 紛紛たり
莫愁前路無知己 愁うる莫かれ 前路に知己無きを
天下誰人不識君 天下誰人か 君を識らざらん
<通釈と解説>
いよいよ師走に入り、寒気団の勢力も次第に強くなってきました。
私は現在、療養のために長野県阿智村に来ています。静かな山村はすでに冬の気配が濃く、寒風に巻かれた落葉が谷間にハラハラと舞い散っていく様は、寒さも省みずに、見佇んでしまう光景です。
さて、慌ただしい年末のこの時季の詩として、今回は『唐詩選』から高適の「別董大」を読みましょう。スケールの大きな冬の風景としてとらえてみましょう。
[口語訳]
千里彼方まで巻き上がる黄塵に太陽も暗くくすむ。
北風は南への雁を追い立てるように吹き、雪が激しく降ってくる。
心配はしないでくれ、行く先に友がいないなどとは
この世に君を知らない者など誰がいるはずがあろうか。
起句は「十里」というテキストもあるそうですが、ここは「黄雲」の広がりを大きくとらえるためにも「千里」と行きたいところですね。地平線の彼方までも広がる黄塵が、太陽までも覆うようだ、そんな勢いを読み取りたいと思いませんか。
詩人としては名高い高適ですが、若い時は不遇な時代が続いたようです。光の衰えさせられた「白日」は作者の投影という見方もあります。
高適は、詩人としての活動するのは遅いのですが、岑参と並び称せられる「辺塞詩人」です。
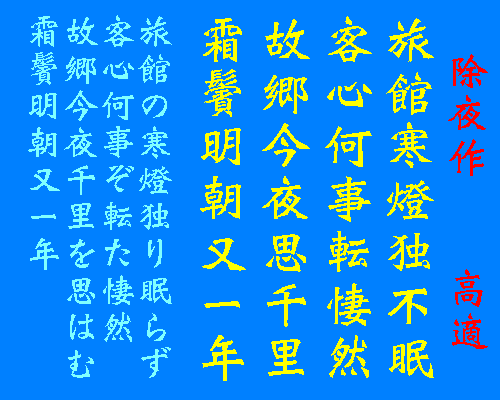
旅館寒燈独不眠 旅館の寒燈 独り眠らず
客心何事転悽然 客心何事ぞ 転(うた)た悽然
故郷今夜思千里 故郷 今夜千里を思はむ
霜鬢明朝又一年 霜鬢 明朝又一年
<通釈と解説>
20世紀もいよいよ終幕へのカウントダウン、冬至の日の落ちる早さに驚きつつ、歳末のあわただしさに翻弄されている毎日ですね。
スキー場の積雪情報も気になりだすと寒さも本番、風邪を引かないように心掛けましょう。
今年最後の「お薦め漢詩」は、前回と同じく、盛唐の高適の代表作『除夜作』を読みましょう。
[口語訳]
旅館の寒々とした灯火の下で、独り眠れずにいて、
旅の思いはどうしたことか、ますます寂しさを増してくる。
故郷を思うと今夜、千里の遠さが胸に迫り、
霜のように白い鬢は明朝、また一つ年を重ねることだ。
この詩は、作者がまだ不遇の時代に作られたものでしょうか。鬢に白いものが増えてきてもなお前途の見えない不安と寂しさがにじみ出てくる作品です。
「旅館」「寒灯」「独」「客愁」と畳みかけるように状況を詠みあげて、一気に旅先の除夜に読者を連れていってしまいます。圧巻は、後半の対句、「故郷・・思千里」という遙かな想いと、眼前の鏡に映る自分の「霜鬢」の遠近の対比で、この対によって、詩の主題が旅の愁い(これだけならよく目にする旅の詩ですね)から、自分の現実を見据えた人生の愁いへと広がっていくことになります。
転句の訓読については、「故郷は今夜千里を思はん」と読んで、「故郷の人々は今夜、千里遠くの私を思っているだろう」という解釈もあります。主語の逆転になりますが、実際の詩情としては違いは微妙ですね。皆さんは、どう読みますか?