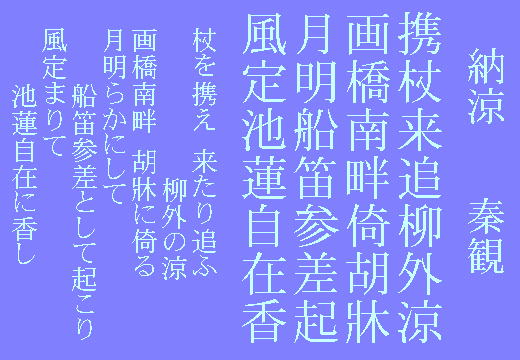
解説は画像の上で左クリックすると出ます
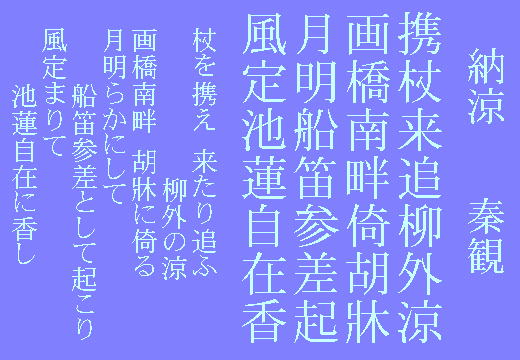
携杖来追柳外涼 杖を携え 来たり追ふ 柳外の涼
画橋南畔倚胡牀 画橋南畔 胡牀に倚る
月明船笛参差起 月明らかにして 船笛参差として起こり
風定池蓮自在香 風定まりて 池蓮自在に香し
<通釈と解説>
[口語訳]
杖を携えて、柳の向こうの涼味を求めて来た。
きれいな橋、川の南のほとりで、長椅子にもたれる。
月は明るく、船の警笛が時折起こり、
風はおさまり、池の蓮の香が四方に漂っていることよ。
七夕の日でしたので、「七夕の詩」を掲載しようか、どうしようかと悩みましたが、新暦ではどうもイメージが違います。旧暦では今年の七夕は八月六日、立秋の前日、秋の気配が感じられる頃にしましょう。
昼の暑さに耐えながら迎える、夕方の涼。それを何で描くかが詩人の勝負所ですが、この詩では、視覚・聴覚・嗅覚を配置して、全身で感じ取ろうとする姿が浮かびます。
「一つだけでも十分だ!」という方も居られるかもしれませんが、毎日こんな好条件というわけではありませんから、この日のこの時の一瞬を描きたかったのだと思います。
あれもこれも並べると、どうしても「作り物」めいた感じがして来ますし、散漫な印象が強くなります。何よりも、私などはひがみ根性からか、「くそ、うらやましい!」と思ってしまいますが、風景との一期一会を蒸着させる詩人の気迫を読みとるべきですよね。
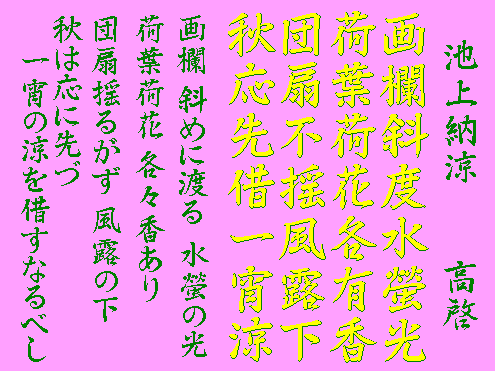
画欄斜度水螢光 画欄 斜めに度(わた)る 水螢の光
荷葉荷花各有香 荷葉荷花 各々香有り
団扇不揺風露下 団扇揺(うご)かず 風露の下
秋応先借一宵涼 秋は応に先づ 一宵の涼を借すなるべし
<通釈と解説>
[口語訳]
きれいな欄干の前を斜めに飛び渡る水辺の螢
蓮の葉も蓮の花も、それぞれが香り高い。
風露蕭蕭の下、団扇を動かすこともないのは、
秋が一夜だけの涼味を、いち早く貸してくれたからだろう。
昼間の狂ったような暑さの後に訪れる夕暮れの一抹の涼。まさに秋の気配を知るわけですが、そんなことを悠長に言っているよりも、冷房のスイッチを入れた方がよほど手っ取り早いのが現代、漢詩や古典に限らず、ホンの20年ほど前の感覚が通用せず、「本を読んでも時代と合わないよ!」という声も聞きます。
でも、現実は現実とした上で、心の中はイメージをどこまででも広げることができる、それが私達の大切な能力です。この能力を前提として、文学は永遠の命を持つのであり、具体的には私達も2000年以上も昔の中国の文章を理解できるわけです。
昨今は、時代の変化を錦の御旗にして、何でもかんでも現代人の感覚に合わなければいけないような風潮、もろもろの文学賞でも「新しい表現の可能性」というだけの理由で選定がなされているように思われるケースが多くなっています。
文学がその時代を描かなくてはならないことは当然ですが、描くだけの時代なのかも考えるべきでしょう。自分が生まれる時代を選ぶことは出来ませんが、時代に自分の意志をぶつけることはできます。くだらない時代であるのに、それを描くためにさらにくだらない表現を使う、それは二重の不幸ですよね。
時代がどれだけ変化しようが、「風の音に秋の訪れを知る」、そうした季節感をいつまでも理解できるように、私達自身の心を保つことこそが未来に向けて健全な道だと思います。
「盛唐の李白の風を持つ」と言われた高啓、彼も不幸な時代の中に生きた詩人でした。しかし、現実からの逃避でもなく、単なるノスタルジーでもなく、伝統をすべて消化し尽くし、自己の時代を自己の言葉で表現した彼は、まさに天才だったと思います。
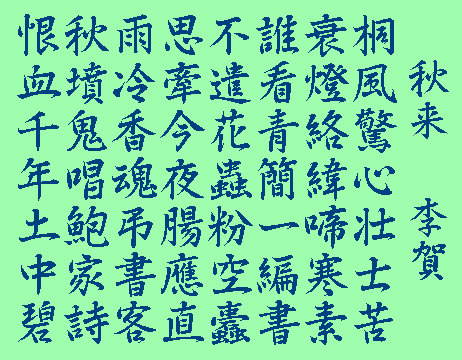
桐風驚心壮士苦 桐風心を驚かし 壮士苦しむ
衰燈絡緯啼寒素 衰灯 絡緯 寒素に啼く
誰看青簡一編書 誰か看ん 青簡一編の書
不遣花蟲粉空蠹 花虫をして 粉(こなごな)に空しく蠹(むしば)ましめざる
思牽今夜腸應直 思いに牽かれて 今夜 腸応に直なるべし
雨冷香魂弔書客 雨は冷やかにして 香魂 書客を弔う
秋墳鬼唱鮑家詩 秋墳 鬼は唱う 鮑家の詩
恨血千年土中碧 恨血 千年 土中の碧
<通釈と解説>
七月の日中の平均気温が平年よりも2度近くも高かったそうで、今年は随分と暑い日が多いようです。
暦の上では、と常套句を言わねばならないわけですが、今日から秋。風の気配にその訪れを感じなくてはいけないのでしょうが、私は何せ病室に入ったままですから、せめて詩で涼しさを感じ取りましょう。
今回の詩は、中唐の李賀、鬼才と呼ばれた異端の詩人の「秋来」を読みましょう。
[語 釈]
「絡緯」:キリギリスの類
「寒素」:冷たい白布・月光の形容
「青簡」:書物
「花蟲」:紙魚
「鮑家」:六朝の詩人・鮑照
[口語訳]
桐の葉を吹く風に秋の訪れを初めて知り、
心丈夫な筈の私もたまらなくなる。
消えそうな燈火の下、キリギリスが
冷たい月光を浴びて啼いている。
私の一巻の詩集を誰が読んでくれようか。
紙魚に空しく食べさせて
粉々にさせるだけのことではないだろうか。
そんな思いに引きずられて、今夜
私の腸はきっと伸びて死んでしまうのだろう。
そうしたら、雨が冷たく降る中で
昔の詩人の霊魂が詩人( 私 )を訪ねて来よう。
秋の寂しい私の墓では
霊魂達が鮑照の詩を唱ってくれるだろう。
私の恨みを込めた血は、千年の後に
土の中で凝り固まって碧玉となるだろう。
あまりにも鮮烈すぎるイメージを何とか言葉によって定着させたい、という李賀の作品は、他の唐代の詩人達と比べるとあまりにも作風が違い、とまどう人も多いかもしれませんね。芥川龍之介は李賀の詩のファンであったそうですが。
「長安に男児有り/二十にして心已に朽ちたり」と李賀は自分を詩に詠んでいます。わずか二十七才で死んでしまった天才は、死後、「鬼才」の名を冠せられましたが、彼の詩を読むと、近代の象徴詩をも突き抜けるような李賀の思念の奔流は、時代をも遙かに突き抜けていたのかも、と思います。
ひょっとすると、彼の理解は二十世紀ではまだ不足、次世紀を待つのかもしれません。
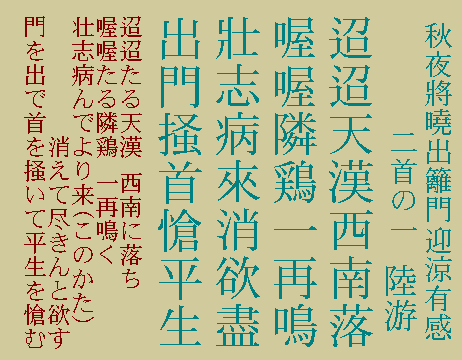
迢迢天漢西南落 迢迢たる天漢 西南に落ち
![]()
![]() 隣鶏一再鳴
隣鶏一再鳴 ![]()
![]() たる隣鶏 一再鳴く
たる隣鶏 一再鳴く
壯志病來消欲盡 壮志 病んでより来(このかた) 消えて尽きんと欲す
出門掻首愴平生 門を出で首を掻いて 平生を愴(いた)む
<通釈と解説>
秋の気配と夏の名残とがしのぎ合い、季節の移り変わりを本当に実感する頃となりました。
個人的な話になりますが、この8月23日処暑の日に、五十日間の病院生活からようやく解放され、家に戻りました。病院は空調設備も整っていて、朝から晩まで(夜中まで)快適な温度に室内は保たれていたため、あまり気候の変化を感じなくなっていました。
家ではクーラーをかけて寝る習慣はありませんから、退院したら夜は寝苦しいかな?と予想をし、掛け布団も用意せずに寝たのですが、何と冷えて夜中に目を覚ます始末。秋はすぐそこまで来ていたのですね。
さて、そんな季節にふさわしい詩は何だろうか、と探すと色々あるのですね。やはり、こうした季節の変わり目は詩人の心を動かすのでしょう。
又、特に病室で詩を読んでいると、どうしても「先人は病気の時にどんな詩を作ったのだろうか?」と気になって、つい「病」とか「患」なんて字を見ると目が行ってしまったりということで、今回は南宋の陸游の詩を選びました。
[語 釈]
「![]()
![]() 」:鶏の鳴く声
」:鶏の鳴く声
[口語訳]
はるか遠くの銀河は西南の空に落ちていき
コッコッと隣の家の鶏が一声二声と鳴いている
病気をして以来、どうにも気力が出て来ない
門を出て頭を掻きながら、日頃の己を悲しむことよ
陸游は南宋を代表する詩人であると共に、北の国である金の圧迫に抵抗する強い愛国心を吐露した詩が多くの人に愛されています。中でも、死の数日前に作った辞世の詩、『示児』は、「死しても尚、国を憂う」という心情が詠われて有名です。
この詩にはそうした憂国の情は直接には描かれていませんが、同題の「二」の方では、「金に北の領土を全部奪われてしまった」という内容で悲しみを強く詠い上げています。従って、この「一」の詩も当然、「壮志」「愴平生」の指す意味は国を憂うることとつなげて理解すべきでしょう。
「壮」は「三十代の若い頃」の意味、「平生」は「人生・一生」の意味が正しいと思います。
しかし、今回は私は自分の状況と重ねてこの詩を読みました。そうした読みは誤解を招くかもしれませんが、今回だけはお許しいただきたいと思います。
勿論、だからと言って、私の現在の心境がこの詩の訳のように、ドドーンと落ち込んでいるというわけではありません。「陸游さんも病気の時は、きっと元気が無くなったんだよな」という親近感というか、安心感というか、そんな感じですね。
気力を今から高めていきますから、大丈夫ですよ。
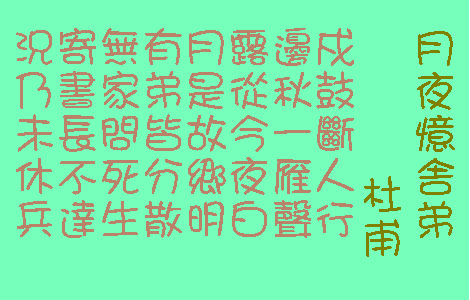
戍鼓斷人行 戍鼓 人行断え
邊秋一雁聲 辺秋 一雁の声
露從今夜白 露は今夜より白く
月是故郷明 月は是れ故郷に明かるからん
有弟皆分散 弟有れども皆分散し
無家問死生 家の死生を問ふべき無し
寄書長不達 書を寄するも長く達せず
況乃未休兵 況んや乃ち兵を休めざるをや
<通釈と解説>
めっきりと秋らしい風を感じるようになりました。明け方などに、空気の冷たさに目を覚ますことも多く、病み上がりの身には過ごしやすく幸いに思っています。
気候は白露、露が白く降りる頃ということですが、秋も中盤。
高啓の『中秋』の詩に、
此夕月華流 此の夕 月華流れ
応分一半秋 応に分かつべし 一半の秋
という名句がありますが、秋と月は切り離せませんね。
そんなこんなで、今月の推薦詩としては、杜甫の「月夜憶舎弟」を読んでいただきましょう。
[口語訳]
砦の太鼓が鳴り 人通りは絶えて
辺境の秋空には 一羽の雁の声が響く
今夜からは白露の季節
月光は故郷をも明るく照らしていることだろう
弟たちはバラバラになって暮らしており
759年秋、杜甫48歳、官職を捨て、家族と共に漂白の生活を始めた頃の作です。この後、暮れには成都にたどり着くのですが、この年齢で職も家も名も捨てねばならなかった詩人の心には、秋の露は重く悲しかったろうと思います。
私は丁度、この時の杜甫と同じ年齢になりましたが、そう思って読むからでしょうか、最近は杜甫の詩がしみじみと実感を伴って胸にしみて来ます。
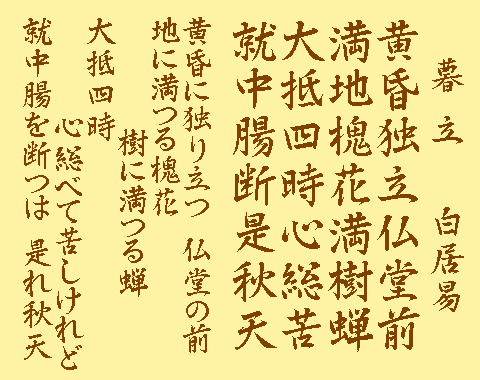
黄昏独立仏堂前 黄昏に独り立つ 仏堂の前
満地槐花満樹蝉 地に満つる槐花 樹に満つる蝉
大抵四時心総苦 大抵四時 心総べて苦しけれど
就中腸断是秋天 就中腸を断つは 是れ秋天
<通釈と解説>
秋分の日を境にして、朝晩の涼しさが強く感じられる頃、オリンピックに心を奪われている内に、私は風邪を引いてしまいました。
さて、秋も真っ盛りの「お薦め漢詩」、今回はお彼岸も意識して、白居易がお母さんを亡くした年の秋に創った『暮立』という詩を選びました。
[口語訳]
黄昏にひとり、仏堂の前に立てば、
地面を覆う槐花と樹に満ちる蝉の声。
そもそも四季はそれぞれ、みな心を悲しませるものだが、
その中でもとりわけ、腸のちぎれるような想いのするのは秋だ。
白居易は四十歳の時、お母さんを亡くしたということです。
この詩は、その年の秋、喪に服している時に作られました。
起句の「仏堂前」が無ければ、単なる秋の詩としてありきたりのものかもしれませんが、この語句によって「独立」という言葉がより意味を強くしてきます。
私たちは様々な場面で孤独を感ずるわけですが、愛する人や常に傍にいた居た人が居なくなった時は特にその思いが強くなります。同時に、状況として哀惜の気持ちを誘うもの、この場合は承句の「満地槐花満樹蝉」が一層寂しさを強めることでしょう。
秋は夕暮れ、もののあはれを知るのも秋、これは古来言われ続けたことで、白居易の発見でも何でもありませんが、墓前にたたずむ彼岸の場面を重ねて、しみじみと共感を呼ぶ詩となっています。
作者の創作時の特殊状況を加味しなくても、(つまり母を亡くした時の詩だと限定しなくても)勿論この詩は秋の詩として鑑賞に値するものでしょうが、でも、この折りの悲しみを理解した方が一層味わい深い気がします。
先日、授業で、正岡子規の
「いちはつの花咲き出でて我が目には今年ばかりの春往かむとす」
という短歌を鑑賞しました。
子規の夭折を知る私たちは、下の句を「自らの死を意識した上での、最後の春を惜しむ気持ち」が表現されたものととらえるのですが、生徒には「今年の春は今年しかない、今の一瞬を愛おしむ気持ち」の表現としてとらえた者もいました。作者の置かれた状況を考慮すべきか否か、と言うよりも状況を考慮しなくては歌として成り立たないのかどうか、問題を提起しただけで終わりましたが、面白い内容でした。