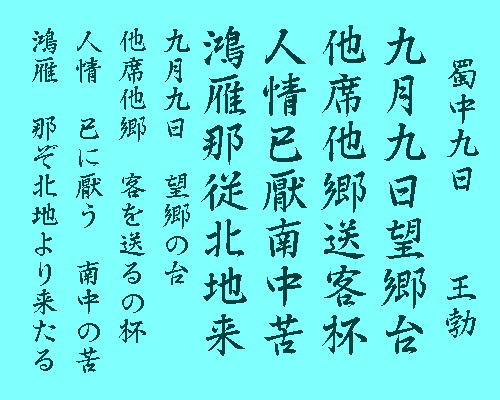
解説は画像の上で左クリックすると出ます
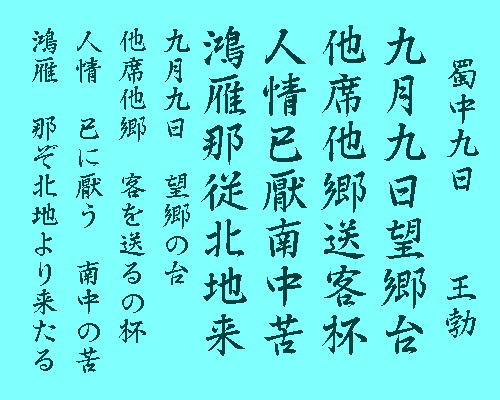
九月九日望郷台 九月九日 望郷の台
他席他郷送客杯 他席他郷 客を送るの杯
人情已厭南中苦 人情 已に厭う 南中の苦
鴻雁那従北地来 鴻雁 那(なん)ぞ北地より来る
<通釈と解説>
「おや、もう10月なのに、『九月九日』は変じゃないですか?」と、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、今回は旧暦(10月17日)で行きましょう。
王維の『九月九日憶山東兄弟』や杜甫の『登高』に窺われるように、この重陽の節句には、一族そろって高い丘に登って、菊酒を飲むのが習慣だったそうです。
故郷を離れた人にとっては、家族とのかつての楽しい時を思い出すとともに、高い所から遠くを望むことから故郷を偲ぶ機会だったようですね。
今回は、初唐の王勃の作品、『唐詩選』では「七言絶句」の一番初めに載せられている作品ですので、目にした方も多いと思います。
訳は、江戸時代の服部南郭先生にお願いしましょう。
[口語訳]
九月九日には高い処へ上るものぢゃと云ふにより、
吾も人に誘はれ、蜀の望郷台に上ってみるに、
故郷ならば面白からうが、「他郷」の旅のことではあり、
殊に今日は此の処に別るる人もあるゆへ、いよいよ悲しい。
をれは都より南の方蜀の方へ来ていて、
故郷へ帰ることもならぬに、
鴻雁はどうしたことで北地より来ることぞと、鳥にことよせて云ふこと、
情態がくつろいで面白い。
「望郷台」は特定の場所を表すのではなく、故郷を遠く望む高台という意味での普通名詞と解釈した方が良いそうです。せっかく全対格(前半も後半も対句で構成されている)ですので、訓読では「望郷の台」として「の」の字を入れておきました。
転句の「人情」も、誰の気持ちか意見が分かれるところですね。「をれ」と自分のことを指すともとれますし、「鴻雁」に対比して人一般を指すともとれます。ただ、どちらにしても、故郷へ帰りたいのは誰よりも作者自身であることは間違いありませんね。
王勃はわずか二十八才で海に落ちて溺れて死んでしまったそうですが、才能は豊か、しかし、人柄は最悪だったようで、当時の科挙の試験官が初唐の四傑を指してこう言ったそうです。
「(王)勃等は文才有りと雖も、而も浮躁浅露なり。
・・・・令終を得れば幸いと為す」
(『旧唐書』「王勃伝」より)
簡単に言えば、「王勃等は文才は有るが、軽薄で底が浅い。まともな死に方ができたらもっけの幸いだろう」と言っているわけで、こりゃあひどいぜって感じですね。
しかし、転句から結句にかけての対比の発想などは、切々とした実感がこめられているようで、私は軽薄なだけの人柄とはなかなか思えません。王勃の他の作品、例えば『古文真宝後集』に収められている「滕王閣序」なども、あふれんばかりの才能の叫びを感じますね。
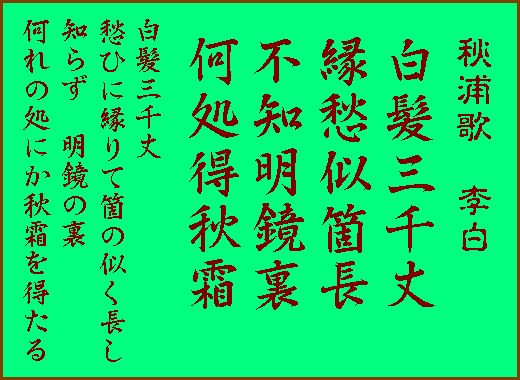
白髪三千丈 白髪三千丈
縁愁似箇長 愁ひに縁りて箇(かく)の似(ごと)く長し
不知明鏡裏 知らず 明鏡の裏(うち)
何処得秋霜 何れの処にか秋霜を得たる
<通釈と解説>
いよいよ秋も終わりに来ました。朝晩の冷え込みが強く感じられる頃、そして「二月の花よりも紅なり」と詠われた「霜葉」の季節、霜と言えばやはり、李白のこの詩でしょうね。
今回も、服部南郭先生の名訳でお楽しみ下さい。
[口語訳]
鏡で見れば、我が白髪の長さ、三千丈もある。
このやうに髪の長くなると云ふは、されば愁へのあるゆへに、
このやうに長くなった。
髪の白いと云ふは、霜を置いたやうぢゃ。
これはどこから得たことぢゃ。吾も知らぬと、甚だ驚いた様子ぢゃ。
「白髪三千丈」などと云ふは、白ができ口である。
最後の「白ができ口である」というのは、「李白がうまく思いついた表現」という意味だそうですが、「不用意」なるをもって「唐詩三百年に一人の絶句の天才」と唱われた李白の面目躍如の一句ですね。
李白の秋の詩は、どれもあまりにも有名で、この「秋浦歌」もあらためて推薦する必要もないくらいですね。
私は最近、この「三千丈」が単なる誇張ではないように、妙に実感を伴って感じられるようになりました。自分の半生をふと振り返った時のあの切ない感触、それはまさに、丁度「三千丈」でぴったり、そんな気持ちになるのです。
だからどうした?と言われると困りますが、ま、そんなことでお薦めします。(なんのこっちゃ)
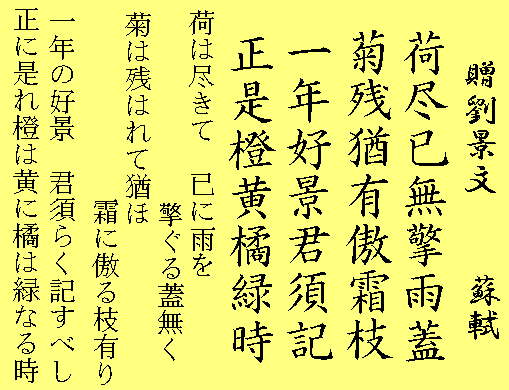
荷尽已無擎雨蓋 荷(はす)は尽きて 已に雨を擎(ささ)ぐる蓋(かさ)無く
菊残猶有傲霜枝 菊は残(そこな)はれて 猶ほ霜に傲(おご)る枝有り
一年好景君須記 一年の好景 君須(すべか)らく記すべし
正是橙黄橘緑時 正に是れ 橙(ゆず)は黄に橘(みかん)は緑なる時
<通釈と解説>
いよいよ冬になりました。この季節は花も紅葉も無く、なかなか詩にはなりにくいわけですが、そんな常識に反逆の炎をあげたのが蘇軾のこの詩です。
[口語訳]
蓮の花は散り果てて、雨を防ぐ傘のようなあの葉ももう無い。
菊の花もしおれてしまったが、
それでも霜に負けずに胸を張る枝はやはりある。
一年の中で最も良い風景を、君、是非心に留めるべきだ。
今は丁度、柚が黄色に熟れて、蜜柑がまだ緑の(素晴らしい)季節なのだ。
秋の深まりが遅く、紅葉を味わう暇もあまり無いうちに冬が来てしまいました。
実はこの2、3日の朝方の冷気に風邪をひきかけていて、喉も足腰も痛くなりかけています。みなさんも、季節の変わり目、お気をつけ下さい。
さて、この『お薦め漢詩』もしばらく唐代の詩が続きましたが、いよいよ宋の蘇軾の登場です。
詩は時代が下れば下る程、描かれる詩想はより新しいものが求められます。夏の蓮の花と雨、そして秋の菊と語って、全てが霜枯れる殺風景な冬のこの季節を「一年好景」と言い切る力強さ、「詩の展開の真髄がここにあるのだ!」と胸を張る蘇軾の顔が目に浮かぶようです。(そうそう、「作者からの挨拶」のコーナーの写真を、蘇軾に戻しましたから、また見て下さい)
花がないと嘆く前に他のものを探せ、その発想こそが大切だと思います。
現代は、いろいろな面で満たされている分、不足に対してあきらめが早くなっている気がします。「この機能がないから仕方がない」とか、「このことは習っていないから出来ない」とか、限界をすぐに決めてしまっていないでしょうか。
もっと貧しければ、何とか代替機能を探したりとか、試行錯誤を繰り返したりとか、現状で更に向上するための努力をするだろうに、ものがないことに責任を移して逃げてしまうことが多い、自分の生活を振り返っても、反省する場面がたくさんあります。
貪欲に、他人には見えないものを見分ける視点を、いつも持ち続けたいと思います。
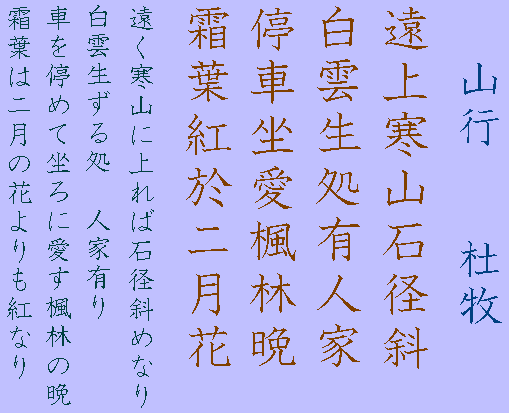
遠上寒山石径斜 遠く寒山に上れば石径斜めなり
白雲生処有人家 白雲生ずる処 人家有り
停車坐愛楓林晩 車を停めて坐(そぞ)ろに愛す 楓林の晩(くれ)
霜葉紅於二月花 霜葉は二月の花よりも紅なり
<通釈と解説>
晩唐の杜牧の代表作、『山行』を今回は推薦しましょう。
先日、京都の嵐山に紅葉を見ようと出かけました。11月の中旬でしたが、茶色く変わっているだけで、鮮やかさは全くありませんでした。
その折に聞いた所では、「今年は夏が暑く、しかも秋深くまで暖かさが続いたため、どうも色づきが悪い。このまま落葉してしまうだろう」とのことでした。となると、「二月の花よりも紅」の風景に出会わないままに冬を迎える方も今年は多そうですから、杜牧の詩で美しい紅葉を想像していただきましょう。
[口語訳]
はるばると晩秋のもの寂しい山に登ると、
石混じりの小道が斜めにずっと続いている。
白い雲が湧き出るような、こんな奥深い山に
ひっそりと人の住む家が見える。
私は、この楓の林の夕暮れを静かに眺めようと車を停める。
霜に打たれて色づいた葉は、何と二月の桃の花よりも紅いのだよ。
転句の「坐」をどう解釈するかが問題となっていますが、日本人に長年親しまれてきた「そぞろに」という読みも捨てがたく、折衷のような訳にしました。
結句があまりにも有名ですが、私は、その前に置かれた「石径」や「人家」という素材が、この詩のリアリティを醸し出していると思っています。
構成から見れば、「寒山」「石径」「白雲」と並べて人里離れた状況を作りつつ、その寂しさの中に「楓林」の鮮やかさを強調する、桃源郷の「桃」に対抗させた異次元の「紅」色を描きたい気がします。
しかし杜牧は、その誘惑を断ち切って、「人家」を配置することで詩の世界を現実に引き戻します。その上で改めて、夕暮れの楓林を示している。
例えば、藤原定家の三夕の歌、
見渡せば花も紅葉も無かりけり
浦の苫屋の秋の夕暮れ
などは、「何も目に映る美しい風景は無い」と言いつつも、そこに「苫屋」があることで、秋の寂しさを一層引き立てる役割を狙っています。
同じように杜牧のこの詩も、「人家」を置くことで晩秋の寂しさをより強調する効果はあるのでしょうが、それ以上に私には、リアリティを求めたように思います。
隠者や仙人だけが見ることのできる風物、そういうものではなくて、誰でも見ることのできる美しい自然、毎年繰り返される自然の営みを描いているのだ、と私は思います。
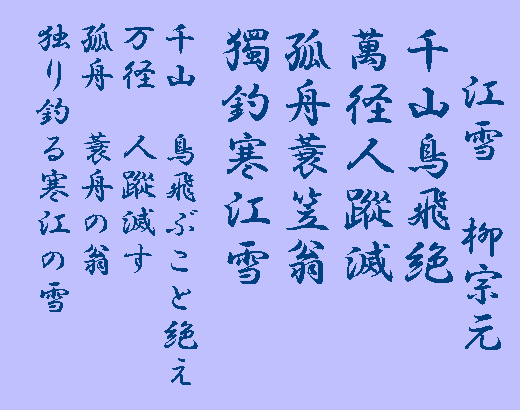
千山鳥飛絶 千山鳥飛ぶこと絶え
万径人蹤滅 万径人蹤滅す
孤舟蓑笠翁 孤舟蓑笠の翁
独釣寒江雪 独り釣る寒江の雪
<通釈と解説>
説明の必要のないくらい有名な、柳宗元の『江雪』を12月の詩として読みましょう。
暖冬とは言われながらも、今日などは寒さが骨身にしみるような日でした。
[口語訳]
遥かに山々の嶺を見れば鳥の飛ぶ姿も見えず
幾条もの小道では人の足跡も雪に消えた
舟を出しているのは蓑笠じじいのこの私だけ
雪の降りしきる川で独り釣り糸を垂れることよ
「人知を超えた、天が作ったような詩だ」とこの詩を絶賛したのは、宋の蘇軾だそうですが、本当に、たった二十字の中に一つの世界が凝縮されている気がします。
作者が永州に流されていた時に作られた詩ですが、「寒江」が己の境遇を象徴しているとか、釣り糸を垂れるのはどんな意味があるのか、など、様々な見解が出ているようですが、そうした隠されているものを探るよりも、先ずは純粋に詩が描き出している世界を心に思い描きたいと思います。
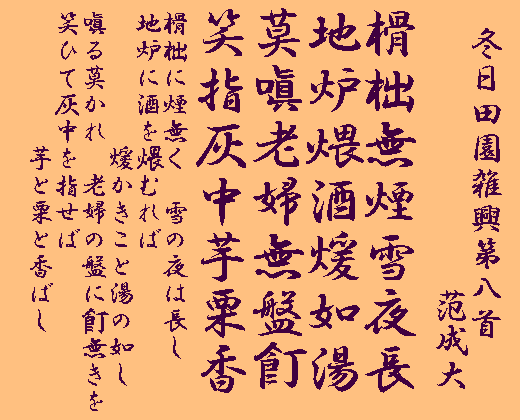
榾柮無煙雪夜長 榾柮に煙無く 雪の夜は長し
地炉![]() 酒煖如湯 地炉に酒を
酒煖如湯 地炉に酒を![]() (あたた)むれば 煖かきこと湯の如し
(あたた)むれば 煖かきこと湯の如し
莫嗔老婦無盤![]() 嗔(いか)る莫かれ 老婦の盤に
嗔(いか)る莫かれ 老婦の盤に![]() (つまみ)無きを
(つまみ)無きを
笑指灰中芋栗香 笑ひて灰中を指せば 芋と栗の香ばし
<通釈と解説>
1999年の最後の推薦詩を何にしようかと、随分迷いました。
慌ただしい毎日ですが、ほっと一息つく夜の時間も良いものです。そんな雰囲気を感じさせる詩を選んでみました。
榾柮(そだ:木の切れ端)は真っ赤に燃えて煙りも出ず世紀末の世相なのか、この年末になって悲劇的な事件が新聞の一面をにぎわしています。
雪の夜はことさらに長い。
地面に掘った炉で酒を温めれば
その温かさはお湯のようだ。
怒ってはいけないよ
婆さんが酒の肴を用意してないことを。
笑って指さす先を見れば
灰の中には里芋と栗が香ばしく焼けていることだ。