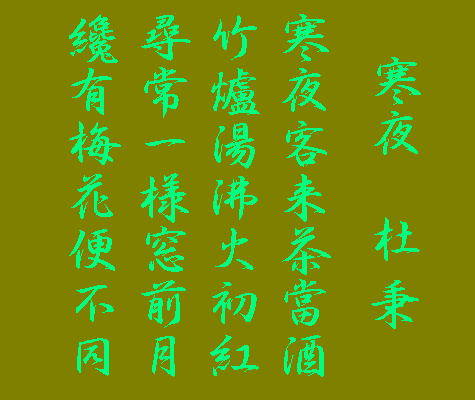
解説は画像の上で左クリックすると出ます
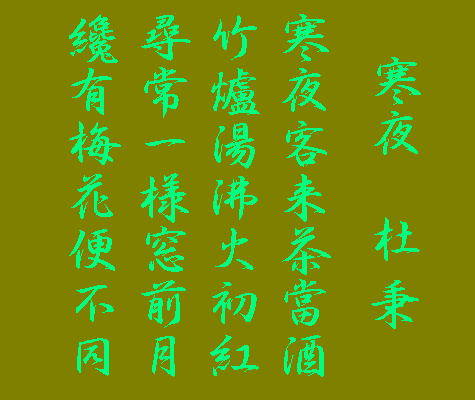
寒夜客来茶当酒 寒夜客来たりて 茶を酒に当つ
竹爐湯沸火初紅 竹爐 湯は沸きて 火初めて紅なり
尋常一様窓前月 尋常一様 窓前の月
纔有梅花便不同 纔(わず)かに梅花有りて 便(すなは)ち同じからず
(上平声「一東」の押韻)
<通釈と解説>
新年あけましておめでとうございます。
二十四節気を漢詩とともに味わいたいという主旨の、この『お薦め漢詩』ですが、四年目を迎えました。
「その内にはネタ切れになって自動的に終わるだろう」と思っていた企画も、漢詩の奥深さか、これは果てしなく続きそうですね。私自身にとっては結構なプレッシャーではありますが、同時に改めて愛読の詩を読み返したりして勉強になりますので、本当に「ネタ切れ」になるまでは頑張りますので、今年も宜しくお付き合いください。
さて、元日の穏やかな天気から一転、数十年ぶりという大雪に見舞われた日本列島。何となくこの一年の前途に不安なものを感じたのは、はて、私だけでしょうか。
厳しい寒さの中でも、ほんの少しでも希望や期待は持ちたいもの。ということで、今回は南宋の杜秉(とへい)の「寒夜」を読みましょう。
[口語訳]
寒い冬の夜 訪れた客には お茶を酒の代わりに出そう
竹編みの爐には湯が沸いて 火が赤く燃えたばかり
窓の外にはいつもの通りのお月様
でも、梅が少しほころんだから、どこか違って見えるね
転句の「尋常一様窓前月」という、寒い冬の夜の月をまずズバリと出しておいて、でもその月が梅一輪のおかげで今日は少し趣深いと結ぶ展開は、ほんのりとした温かさが漂って来ます。
厳しい寒さの中だけれど一歩先んじて春を感じる、そこに必要なのは希望を持つことかもしれないし、ゆとりを持つことかもしれません。今年がどんな一年になっていくのかは分かりません。でも、春の兆しを少しでも感じ取れるように、毎日を生きていきたいものです。
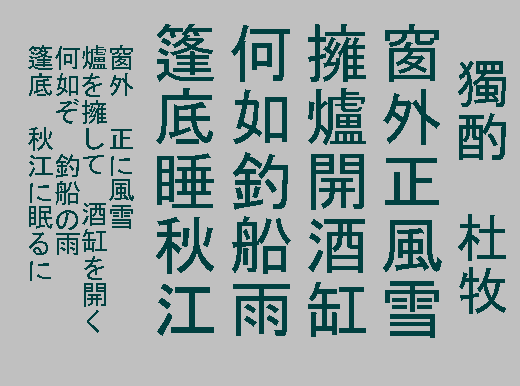
窗外正風雪 窗外 正に風雪
擁爐開酒缸 爐を擁して 酒缸を開く
何如釣船雨 何如(いかん)ぞ 釣船の雨
篷底睡秋江 篷底 秋江に眠るに
(上平声「三江」の押韻)
<通釈と解説>
大寒の今日は、大学入試センター試験の二日目でした。試験の日が雪に降られた年もあれば、雨に濡れた年もありましたが、今年は全国的にもまあまあ穏やかで、試験もひとまず順調に実施されたようですね。
一年で最も寒いこの時季を越えれば、もうすぐそこに春が来ています。受験生の皆さんも、今の厳しい時を乗り切って、素晴らしい春を迎えて下さい。
さて、今回の推薦詩は、晩唐の杜牧の「独酌」という詩です。冬の夜の独りの寂しさと楽しさ、しっとりと味わわせてもらいましょう。
[口語訳]
窓の外はちょうど吹雪のまっただ中、
こんな日には炉端に火を入れて酒瓶のふたを開けよう。
どうだい、秋雨の頃に釣り船の中
川で眠るのと比べてみるのは
この詩の前半は木こりの生活、後半は漁師の生活、という形で、どちらが楽しいかいと尋ねているのですが、勿論、答は「どっちも上々!」が正解です。
そっちも良いけどこっちも良いよ、という感じで、杜牧は何ともうきうきとこの詩を書いてますね。
吹雪の夜なんて本来は厳しい生活である筈ですが、それでもその中に楽しみを見出していく。生きていくこと、生活していくことそのものですね。
こうした感覚は現代では「庶民」の暮らしとしてとらえられるのですが、唐代の漢詩では官に対照するものは「隠者」ですから、ここも隠者の暮らしとして見ることになります。
それだとしても、酒樽を抱きかかえての雪見酒、これには文句のつけようがありませんよね。うーん、受験生とは何にも関係のない展開になってしまいました。
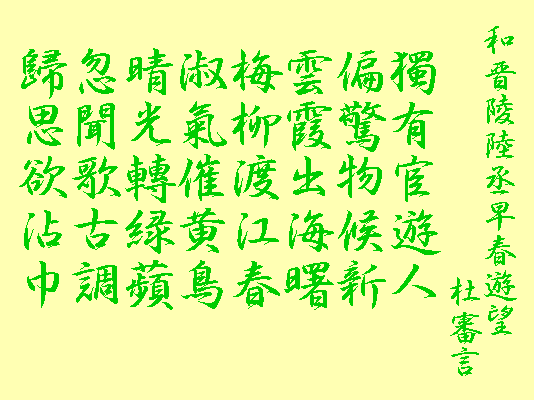
獨有宦遊人 独り宦遊の人有り
偏驚物候新 偏えに驚く 物候の新たなるに
雲霞出海曙 雲霞 海を出でて曙け
梅柳渡江春 梅柳 江を渡りて春なり
淑氣催黄鳥 淑気 黄鳥を催し(うなが)し
晴光轉緑蘋 晴光 緑蘋に転ず
忽聞歌古調 忽ち古調を歌うを聞き
歸思欲沾巾 帰思 巾を沾さんと欲す
(上平声「十一真」の押韻)
<通釈と解説>
外相更迭されて株価暴落という、何とも「風が吹けば桶屋がもうかる」のような話で、先行きの見えない国の状況ですが、季節の方はきちんきちんと春を教えてくれます。
立春の今日は全国的に暖かな日になり、私は散歩をいつもよりも大きく回りました。
馴染みの書店に寄ったら、なんと「閉店のお知らせ」の貼り紙。びっくりしていたら店長さんが現れて、近年の書店事情を話してくれました。そして一言、「最近は本を買う人が少なくなったから・・・」と言われた時に、切ない気持ちで言葉につまってしまいました。
寂しい気持ちで家まで帰りましたが、足取りの重かったこと。つい遠回りしたことを後悔したことです。
立春ですので明るい詩を読もうと思っていましたが、ということで、今回は少し寂し目の詩にしました。『唐詩選』から、初唐の杜審言の「和晋陵陸丞早春遊望」です。
[口語訳]
故郷を遠く離れた孤独の人だけが
季節の風物がすっかり新しくなったことにふと気づくのだ。
海から生まれたような雲や霞、夜は明けて行き、
梅や柳のつぼみは長江を渡って、ここはすっかり春の色。
暖かな風はうぐいすに鳴くことをうながすし、
明るい陽射しは緑色の浮き草に揺れ輝いている。
ふと、なつかしい調べを聞き
帰りたいという気持ちに、涙で袖を濡らしてしまいそうだ。
杜審言は詩聖 杜甫の祖父として記憶に残る人も多いと思います。二十三歳で進士の第に登り、則天武后の頃に宮廷詩人をして活躍をしましたが、才走って人の恨みもかったそうです。左遷の憂き目も見たわけですが、この詩は地方官としての立場で書かれたものですね。
頷聯、頸聯の江南の春景色の描写は美しく、だからこそ一層、尾聯の望郷の想いが暗く切なく浮かび上がって来ます。
また、首聯の「宦遊人」(故郷を離れて地方に勤務している役人)は、尚更季節の変化に敏感になる、というのも、なるほど、と思わせる句ですね。ただ、やや理知的に過ぎると言えばそうかもしれませんが。
頸聯の「催」と「転」の二字には、これ以外には無いというくらいの迫力が感じられる名句ですね。
「暦の上では」ときまり言葉で言われるような、季節の移り変わる端境期の微かな風景を拾い上げた詩人の眼と筆は、杜甫の祖父というだけではなく、一つの時代を代表するに足る才能の持ち主だったことを教えてくれます。
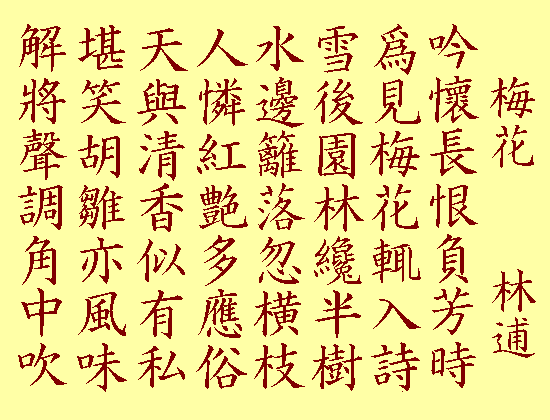
吟懷長恨負芳時 吟懐 長(つね)に 芳時に背くを恨み
爲見梅花輒入詩 梅花を見しが為に 輒(すなは)ち詩に入る
雪後園林纔半樹 雪後の園林 纔(わず)かに半樹
水邊籬落忽横枝 水辺の籬落 忽(たちま)ち横枝
人憐紅艶多應俗 人の紅艶なるを憐れむは 多く応に俗なるべく
天與清香似有私 天の清香を与ふるは 私有るに似たり
堪笑胡雛亦風味 笑ふに堪へたり 胡雛も亦 風味ありて
解將聲調角中吹 解く声調を将って 角中に吹く
(上平声「四支」の押韻)
<通釈と解説>
我が家の狭い庭にも春は訪れ、紅梅白梅が揃って花を咲かせました。と言っても、愛知県でも雨水の十九日には雪が舞い、まだまだ寒さも厳しく続きそうです。
さて、今回は北宋の林逋の「梅花」を読みましょう。林逋と言えば、「山園小梅」が有名ですが、この詩もすばらしいものですね。
口語訳も添えましょう。
詩への思いは、せっかくの花の季節なのにうまく詩を作れないことをいつも恨めしくさせるので、
せめて梅を見た時には、そのたびに詩を作ろうとするのだ。
雪の止んだ後の庭の林に、ほんの少しだけ顔を出す梅の木もよいし、
水辺の生け垣から突然伸びた梅の枝も良いものだ。
人々が紅い艶やかな花を好むのは、なんとも俗っぽいことで
天が清らかな香りを梅に与えたことは特別なことなのだよ。
面白いことに、あの北地の蛮族の子供でも風流が分かるようで、
「梅花落」の曲を角笛の中に吹き入れているよ。
日本の江戸時代、広瀬淡窓が梅の名句に対しての古人の評価を紹介してくれています。
高青邱が「雪満山中高士臥 月明林下美人来」は、林和靖が「疎影横斜水清浅 暗香浮動月黄昏」に及ばず。「雪後園林纔半樹 水邊籬落忽横枝」は又其の上なり。東坡が「竹外一枝斜更好」の七字は、誠に梅の精神を写すものにして、又其の上なりと云へり。『淡窓詩話』
以上の句、俗眼より見れば、古人の卑しと云ひし句ほど面白く覚ゆれども、とくと眼力を養ふて観れば、其の高卑始めて分かるなり。
誰向江南處處栽 誰か江南に向(おい)て 処処に栽ゑたる
雪満山中高士臥 雪は山中に満ちて 高士臥し
月明林下美人来 月は林下に明らかにして 美人来たる
寒依疏影蕭蕭竹 寒には依る 疏影 蕭蕭の竹
春掩残香漠漠苔 春には掩う 残香 漠漠の苔
自去何郎無好詠 何郎の去りしより好詠無く
東風愁寂幾回開 東風 愁寂 幾回か開く
(上平声「十灰」の押韻)
[口語訳]
玉のような姿は、まったく瑶台(月の世界)こそが似つかわしいのに
誰が江南の地のあちこちに植えたのだろうか。
雪は山中に積もり、そこでは梅は心清らかな人が臥しているようであり、
月が林を照らす時には、美人に姿を変えて現れたと言われるのももっともだ。
寒い時には、まだ花の少ないまばらな枝が寂しそうな竹に寄り添うし、
春になれば、残り香が薄暗い苔の辺りにまで覆うように漂う。
何郎がいなくなって以来、梅をうまく詠んだ詩も無く、
春風の中、寂しそうに何度花を咲かせたことだろう。
[口語訳]
多くの花が散りしぼんだ時に、ただひとりで咲き誇り
小さな庭の風情を独占している。
まばらな枝は斜めにのびて、水は浅く清く
かすかな香りは漂い来て 月はたそがれの中
霜のような白い鳥は、舞い降りようとして、(梅の白さに)まず周りをこっそり見回すし、
白い蝶は、もし白い梅花が咲いているのを知ったなら、きっと驚くことだろう。
さいわい、小さな声で吟ずるにふさわしい私の好きな詩がある。
にぎやかな拍子木も酒樽もここには要らないのさ。
只有此詩君壓倒 只だ此の詩有りて 君圧倒す
東坡先生心已灰 東坡先生 心已に灰す
爲愛君詩被花惱 君が詩を愛するが為に 花に悩まさる
多情立馬待黄昏 多情 馬を立てて 黄昏を待つ
殘雪消遲月出早 残雪 消ゆること遅く 月出づること早し
江頭千樹春欲闇 江頭 千樹 春闇(く)れんと欲す
竹外一枝斜更好 竹外 一枝 斜めなるは更に好し
孤山山下醉眠處 孤山 山下 酔ひて眠る処(とき)
點綴裙腰紛不掃 裙腰を点綴し 紛として掃はず
萬里春隨逐客來 万里 春は逐客に随いて來り
十年花送佳人老 十年 花送って 佳人老ゆ
去年花開我已病 去年 花開きて 我已に病めり
今年對花還草草 今年 花に対して 還た草草
不知風雨捲春歸 知らず 風雨の春を捲きて帰るを
収拾餘香還![]() 昊 余香を収拾して 還た昊に
昊 余香を収拾して 還た昊に![]() (あた)へん
(あた)へん
[口語訳]
西湖に隠棲したあの林逋も亡くなってすでに長いけれど
君(秦太虚)はこの梅の詩を作って、彼の人を圧倒している。
私、蘇東坡は心もすっかり灰となっているのだが、
君の詩を好きになってしまって、花の美しさに悩まされることだ。
胸をときめかせて花の前に馬を停めて夕暮れを待てば
残雪は消えること遅く 月は上ること早い。
川のほとりの樹々に春の夕闇が訪れるころ
竹むらのむこう、梅のひと枝が斜めに伸びていて、それが更によい。
孤山のふもとで酔って眠ってしまった時、
登る路には花が乱れて掃うこともない。
万里の彼方に追放された旅人をも追って春は来るけれど、
それでも十年も花を見送っていては、美人でも年老いてしまうもの。
去年は花が開いた時には私はもうすでに病気になっていた。
今年は花に向かいながらも、またもや心落ち着かぬ。
おっと、風雨が春を巻き上げて去っていく。
残り香を拾い集めて、天に送り届けてもらおうか。
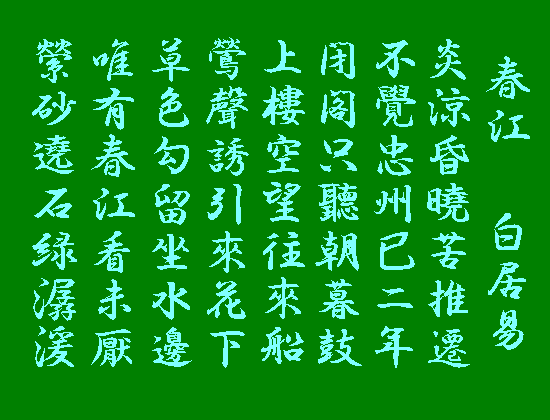
炎涼昏曉苦推遷 炎涼 昏暁 苦くも推遷し
不覺忠州已二年 覚えず 忠州 已に二年なり
閉閣只聽朝暮鼓 閣を閉じて只だ聴く 朝暮の鼓
上樓空望往來船 楼に上りて空しく望む 往来の船
鶯聲誘引來花下 鶯の声に誘引せられて 花の下に来たり
草色勾留坐水邊 草の色に勾留せられて 水の辺に坐(を)り
唯有春江看未厭 唯だ 春江の 看れども未だ厭かざる有り
![]() 砂遶石緑潺湲 砂を
砂遶石緑潺湲 砂を![]() (めぐ)り 石を遶りて 緑潺湲たり
(めぐ)り 石を遶りて 緑潺湲たり
(下平声「一先」の押韻)
<通釈と解説>
一雨ごとに確実に春が近づいてきていることを感じるこの頃ですね。季節ももう啓蟄、虫たちもウズウズとし始める季節、身体を動かして、一歩ずつでも多く外に出るようにしましょう。
さて、今季の推薦詩は、白居易の「春江」です。
[口語訳]
暑さと寒さ、朝と夜が、次々と移りゆき
ふと気づくと、この忠州でもう二年が過ぎた。
高閣の戸を閉めて、朝晩の太鼓の音をひたすらに聴き、
高楼に登っては、行き交う船を空しく眺めている。
鶯の美しい声に誘われて花の下にやってきて、
草の柔らかな緑に引き留められては水辺に腰をおろす。
春の長江は、いつまで見ていても見飽きないものだ。
砂浜をめぐり、岩をめぐって、緑の水がさらさらと流れていくよ。
この詩の頸聯は日本の『和漢朗詠集』に載せられていますので、目にした方、耳にした方もおられるでしょう。
頷聯も、嵯峨天皇と小野篁の故事でも有名です。
嵯峨天皇がこの二句を示すのに、「閉閣只聽朝暮鼓、上樓遙望往來船」と、わざと一字替えて、自作のふりをして小野篁に見せたのだそうです。まだ『白氏文集』は天皇くらいしか見ることができなかったので、当然小野篁も見ていなかった筈なのですが、彼はその句を聞いて、「遙」の字を「空」にした方が良いと言ったとのこと。
小野篁の詩才を表す話なのですが、そう言われてみると、確かに「空」の字はこれしかない、「遙」では良くないよ、と思えてくるから、面白いものですね。
白居易の同時期の作に「春至」がありますので、そちらも紹介しましょう。
春 至
若爲南國春還至 若為(いかん)ぞ 南国 春還た至る
爭向東樓日又長 争ひて東楼に向ひて 日 又長し
白片落梅浮澗水 白片の落梅は 澗水に浮かび
黄梢新柳出城墻 黄梢の新柳は 城墻より出でたり
間拈蕉葉題詩詠 間(しず)かに蕉葉を拈(と)りて 詩を題して詠じ
悶取藤枝引酒嘗 悶(むすぼ)れて藤枝を取りて 酒を引きて嘗む
樂事漸無身漸老 楽事漸く無くして 身漸く老ゆ
從今始擬負風光 今従(よ)り始めて擬す 風光に負(そむ)かんことを
この地、忠州で二度目の春を迎えた心境ですが、穏やかな日々を過ごした江州とは異なり、忠州での生活は白居易にとっては満足できるものではなかったようです。しかし、それでも詩人の眼は、春の到来を的確に捉え、詩人の筆は描き尽くすわけですから、すばらしいものですね。
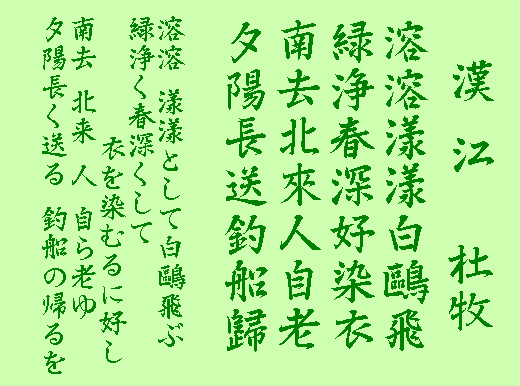
溶溶漾漾白![]() 飛 溶溶 漾漾として 白
飛 溶溶 漾漾として 白![]() 飛ぶ
飛ぶ
緑浄春深好染衣 緑浄く春深くして 衣を染むるに好し
南去北來人自老 南去 北来 人 自ら老ゆ
夕陽長送釣船歸 夕陽 長く送る 釣船の帰るを
(上平声「五微」の押韻)
<通釈と解説>
今年の桜は七十数年ぶりの早咲きだとか、感覚的には二週間は開花が早まっているのではないか、という気がします。「三寒四温」なんて言葉も忘れてしまうような状態であっという間にどっぷりと春になってしまい、人間も自然も、まだ心の準備が出来ていないのにどうしよう、とあたふた。
いや、別に暖かくなったことを嫌がっているのではありませんが、でも、こんなに順調に進むと不安になるのが人間の常ですよね。
漢詩の世界では、春が深まれば深まるほど愁いも深くなる、という詩人の悲しい視点がやはり定番です。
今回は、晩唐の杜牧の代表作、「漢江」を読みましょう。
[口語訳]
ゆったりとした川の水はゆらゆらと光に揺れて その上を真っ白なカモメが飛んでいる。
水の緑は清らかで、春は一層深まっていき、私のこの服までもがこの季節に染まっていきそうだ。
南北に行き来する旅の中で、人はいつか老いていく。
夕陽は何処までも長く、釣り船の帰るのを照らしている。
「溶溶漾漾」は二文字で「溶漾」という熟語もありますが、「水がゆったりと流れ、水面が揺れる」ことですが、こうして「畳字」で並べると、中国語で発音しても「rong2 rong2 yang4 yang4」とリズムが生き生きとした感じを出してきます。
また、転句の「南去北来」は、対句の解釈の基本ですが、もともとは「南北 去来」とあったのを分解して並べ替えた形ですね。決して「南に去り 北に来て」と別々に解釈しないようにして下さい。
起句承句と直接の関わりのないような印象の転句ですが、結句の「夕陽長送釣船歸」と重ねると、はるかな自然の営みの中の、人間のはかない生命が浮かび上がり、しかし、人間の生活も実はこの春の景色の中に入ることを許されているのだということが伝わってきます。
人間は個人としてみれば刹那を生きる小さな存在ですが、人間としての歴史を意識した時には、自然の一員として悠久の中に生き続けている、そんな救いや癒しを与えてくれる詩ではないでしょうか。