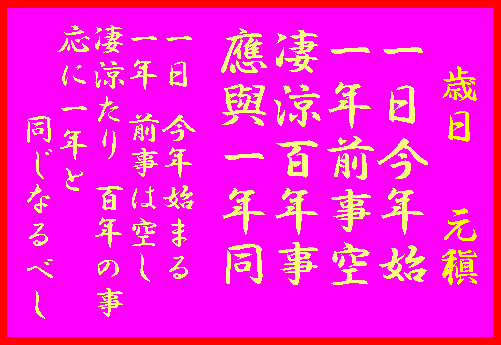
解説は画像の上で左クリックすると出ます
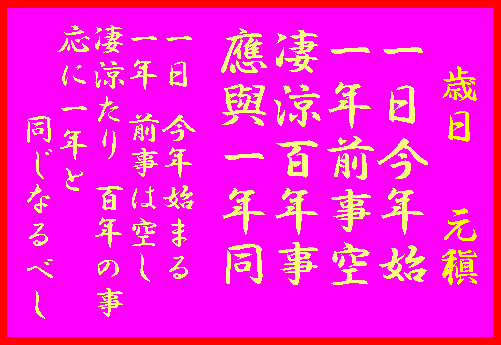
一日今年始 一日 今年始まる
一年前事空 一年 前事は空し
凄涼百年事 凄涼たり 百年の事
應與一年同 応に一年と同じなるべし
<通釈と解説>
漢詩に興味をお持ちの皆さん、いやいや、漢詩がないと一日も過ごすことが出来ないという皆さん、新年明けましておめでとうございます。
去年の正月と今年の正月と、特に何の違いも無いようにも感じますが、でも新しい世紀が始まるというのは腹にぐっと入れておかなくてはいけないと思います。それが百年に一度の節目に生きる者の義務だろうとも思うのです。
流されず、流れず、自分の足元をこの機会にこそ、しっかりと見直すべきなのでしょう。
さて、新世紀のお薦め漢詩のトップパッターは、中唐の元![]() です。白居易との応酬の詩などで名高い詩人ですが、彼の「歳日」という詩で新年を迎えましょう。
です。白居易との応酬の詩などで名高い詩人ですが、彼の「歳日」という詩で新年を迎えましょう。
[口語訳]
今日の日で今年も始まるが、
振り返れば、この一年のことは皆空しく感じる。
百年のことを考えるなんて寂しいものだ。
一年を過ごすのと同じように過ぎていくのだろうよ。
21世紀を迎える日、家族と話していて愕然としたのは、「21世紀ってのは、ドラエモンが生きている時代なんだ!」ということでした。ま、別にドラエモンのファンというわけではないのですが、意識の中では「21世紀なんて、はるか遠い未来のこと」と思っていたのでしょう。そう言えば、「2001年宇宙の旅」もまさに、「2001年」でした。
うーん、未来という明日が今日という日になってしまったという現実を、自分のこととして受け入れるには、まだしばらくかかりそうな気がします。
百年前の日本人はどう思ったのだろうか?と、手元の本を開いてみました。
1901年という20世紀の始まりの日、正岡子規は病床にありながら、こんな短歌を作っていました。
枕べの寒さはかりに新玉の年ほぎ縄をかけてほぐかも
『墨汁一滴』で子規はこう書いています。
病める枕辺に巻紙状袋など入れたる箱あり、其上に寒暖計を置けり。其寒暖計に小き輪飾りをくくりつけたるは病中いささか新年をことほぐの心ながら葉朶の枝の左右にひろごりたるさまもいとめでたし。其下に橙を置き橙に竝びてそれと同じ大きさ程の地球儀を据ゑたり。
この地球儀を眺めながら、子規は「二十世紀末の地球儀はどんな風に色が塗り替えられるのか」と思いを馳せながらも、それは「二十世紀初の地球儀の知る所に非ず」と述べています。世界の中での日本の位置を世紀の始まりに考える、という子規の精神態度は、日本の文化に責任感を強く持っていた明治の文人の一つの象徴でしょう。
同じ年の正月、丁度イギリスに留学していた夏目漱石は、元旦の日記にこう書いています。
英国人ノ裸体画ニ関スル意見ヲ聞ク(Mr.Brettヨリ)英国ニ裸体画少キ所以ヲ知ル
「おいおい、二十世紀の始まりの元旦がそんな話だけで終わりなのかい?!」って感じですね。この年の漱石の日記では、後を読んでいっても正月の雰囲気は全く感じられず、ましてや世紀の節目なんてものは皆無です。
これは考えてみると面白いことで、日本にいた子規の方が二十世紀をより強く感じていて、海外に出ていて広い世界を実感していた筈の漱石の方が逆に、「彼には一九〇一年の元日ではなく、明治三十四年の元日であった。西暦ではなく、明治の年号の意識であって、彼にとっては世紀の変わり目にいるということでなく・・・・」(出口保夫『ロンドンの夏目漱石』より)と指摘されるように、日本から抜け出ていなかったわけです。
21世紀を生きる私たちは、当然のことながら百年前よりもはるかに世界との接点が広いわけです。しかし、だからと言って、世界の中の日本という「地球意識」が本当に深くなっているかと問われると危ういかもしれません。一人一人が自覚的に自分の生き方を考えていかないと、ただ不必要なほどに便利になっただけの精神生活に陥ってしまうかもしれません。
自分の目の前を客観的に見つめていけば、余分に肩を張ることもないでしょう。元![]() の「凄涼百年事」という言葉は、「百年のことなんか考えても空しいだけ」と嘆くものではなく、一年一日をしっかりと踏みしめるように詠ったものと私は思っています。
の「凄涼百年事」という言葉は、「百年のことなんか考えても空しいだけ」と嘆くものではなく、一年一日をしっかりと踏みしめるように詠ったものと私は思っています。
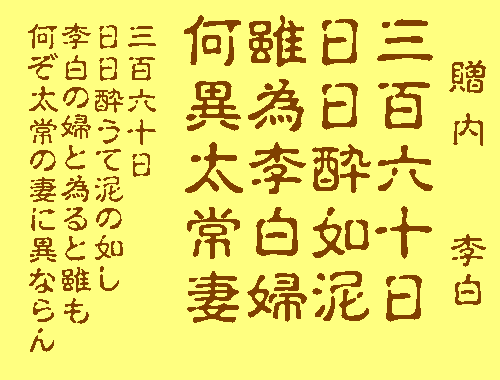
三百六十日 三百六十日
日日酔如泥 日日酔うて泥の如し
雖為李白婦 李白の婦と為(な)ると雖(いえど)も
何異太常妻 何ぞ太常の妻に異ならん
<通釈と解説>
今週に入ってから、かなり大型の寒気団がやって来て、「寒い・・・・寒い!」と震えているだけでは済まず、とうとう大雪になってしまいました。春まであと一歩というところですが、寒さの峠も越えないといけないようです。
大学入試もいよいよシーズンに入り、今日明日とセンター試験の実施日ですが、交通機関などが心配です。昨年はインフルエンザが大流行して心配しましたが、そちらは今年は良さそうですね。
さて、寒さに縮こまっていてもいけませんから、お酒でも飲んで温まるのもよいでしょう。ということでは、やはり酒仙の李白に登場していただきましょうか。
李白とお酒はいくつもの詩がありますが、今回は、李白が妻に贈ったとされる「贈内」と読みましょう。
[口語訳]
一年三百六十五日
毎日毎日酔っぱらって泥虫のよう
李白の妻となったと言っても
太常の女房と同じものだ
少し語注が要るでしょう。
南海に「泥」という骨の無い虫がいるそうで、水中ではしゃきっとしていますが、陸に上がると泥のようになってしまうそうです。
また、「太常」とは、皇帝の先祖を祭る役職で、常に身を浄めていなくてはいけなかったそうです。後漢に周澤という、太常職の男がいたそうです。真面目な人だったようで、一年三百六十日のうち、三百五十九日は仕事のために身を浄めて、決して妻を近づけなかった。そして、たった一日の休暇の日には家で酒を飲み続けてグデングデンに酔っていたそうです。
ある時、この周澤が病気になってしまいました。妻が心配して見舞いに行ったところ、この周澤は身が穢れたと言って腹を立て、妻を牢獄に入れてしまったとか。真面目の上に一文字(二文字?)つきそうな人ですが、この話が結句の下地になっています。
漂泊の俳人、種田山頭火が日記の中で、酒に酔っていく過程を書いてます。曰く、
ほろほろ→ふらふら→ぐでぐで→ごろごろ→ぼろぼろ→どろどろ
いかにも酔いが進んでいく様子が分かります。山頭火の句では、
ほろほろ酔うて木の葉ふる
という名句が思い出されます。
山頭火風に言えば、李白などは年がら年中、「どろどろ」状態に酔っていたのでしょうね。これはまさに、李白の面目躍如でしょうか。
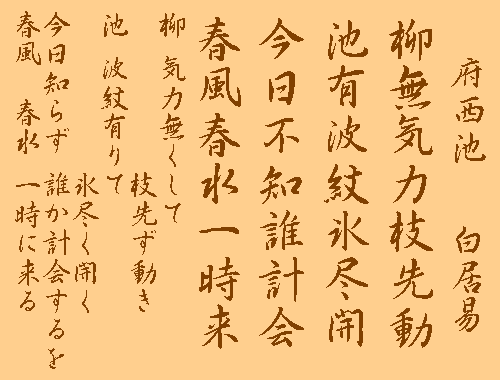
柳無気力枝先動 柳 気力無くして 枝先ず動き
池有波紋氷尽開 池 波紋有りて 氷尽(ことごと)く開く
今日不知誰計会 今日知らず 誰か計会するを
春風春水一時来 春風春水 一時に来る
<通釈と解説>
節分の豆まきをした後に拾って食べる豆の数がだんだん多くなり、食べるのが辛くなってきたぞ、と思うともう春なんですね。
寒さも峠を越えたのでしょうか、立春を迎えて、気持ちの上では少し暖かくなったように感じます。
さて、今年の立春の漢詩は、『和漢朗詠集』にも載せられました白居易の「府西池」を読みましょう。
[口語訳]
柳は力無さそうにして 枝の先が風に揺れ
池には波紋が広がって 氷が皆とけてゆく
今日のこの様子は誰が一体計算したのか
春の風と春の水が一度にやって来るなんて
起句と承句の対句が非常に印象的で、立春の浮き立つような景が目に浮かびます。特に起句の「柳無気力枝先動」の細やかな観察と丁寧な表現は、才がはじけたような、力強さを感じますね。
転句結句はやや理屈っぽく感じますが、「春風春水一時来」のリズム感は、春を迎えての心の躍動につながるような、記憶に残る一句ですね。
古今和歌集を代表する歌人、紀貫之の歌
袖ひぢてむすびし水のこほれるを
春立つ今日の風やとくらむ
も、「春風」と「春水」とを織り込んだ、やはり立春の名歌です。
紀貫之のこの歌は、「袖ひぢてむすびし水」(袖を濡らして手ですくって飲んだ水)に 夏 を詠い、その水が「こほれる」により 冬 を詠い、更に「春立つ今日」と 春 を詠むという、三十一文字の中に三つの季節を入れたという工夫も光るところです。
・・・・暦の上では・・・・という口上がつかない、正真正銘の春を実感できるような、暖かな日を私は待ち望んでいるのですが、まだ、もう少しかかるでしょうか?
庭の梅の蕾も待ちわびています。
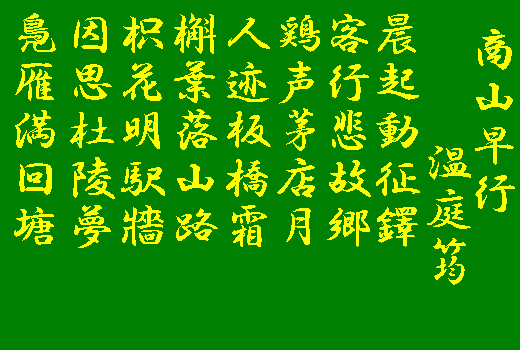
晨起動征鐸 晨に起きて征鐸を動かす
客行悲故郷 客行 故郷を悲しむ
鶏声茅店月 鶏声 茅店の月
人迹板橋霜 人迹 板橋の霜
槲葉落山路 槲葉(こくよう) 山路に落ち
枳花明駅牆 枳花 駅牆(えきしょう)に明かなり
因思杜陵夢 因りて思ふ 杜陵の夢
鳧雁満回塘 鳧雁 回塘に満つ
<通釈と解説>
立春を経て二週間、そろそろ春の気配も感じられるかと思う矢先に、必ず寒の戻りといいますか、最後(になってほしい)の寒波が訪れますね。ここに来て、風邪をひき直した方も多いのではないでしょうか(かく言う私もですが・・・)
氷も溶けて野も山も雨や水に潤うという「雨水」にふさわしい景はいつ見られるでしょうかね。
さて、そんな春とは言えまだ寒いこの季節の「お薦め漢詩」は、晩唐の温庭![]() (おんていいん)の名作、『商山早行』です。この詩は季節が春なのか冬なのか、意見が分かれていますが、「槲葉」は「かしわの葉」で、「その葉は冬の間枝についたままで、春に新芽が伸びるときになって落ちる」(東京堂書店・『唐詩鑑賞辞典』)ですし、「枳花」は「からたちの花」ですから春開きますので、前半の「板橋霜」にまどわされずに、早春の詩と見ておきましょう。
(おんていいん)の名作、『商山早行』です。この詩は季節が春なのか冬なのか、意見が分かれていますが、「槲葉」は「かしわの葉」で、「その葉は冬の間枝についたままで、春に新芽が伸びるときになって落ちる」(東京堂書店・『唐詩鑑賞辞典』)ですし、「枳花」は「からたちの花」ですから春開きますので、前半の「板橋霜」にまどわされずに、早春の詩と見ておきましょう。
[口語訳]
朝早くから起きて車の鈴を鳴らして出発すれば
旅のことゆえ、故郷が悲しく思い出されるもの
夜明けを告げる鶏の声、茅葺きの旅館の屋根にかかる月
人の足跡が冷たく、板橋の霜の上に残っている
かしわの葉が山道に落ちて
からたちの花が駅舎の塀に咲いている
春に気付いた胸の中に、長安の都杜陵でのことが思い出される
雁どもが池に群れていた、あの杜陵でのことが・・・・
晩唐の温庭![]() につきましては、森
につきましては、森![]() 外の小説『魚玄機』に詳しく書かれていますが、「鍾馗」さまのような鬚のはえたたくましい顔で、豪放な人物だったようです。歯に衣を着せぬ言動のために科挙も受からなかったそうですが、「八たび手を叉(こまぬ)けば八韻の詩が成るので、温八叉(おんはっさ)と云う渾名」があるそうで、つまり腕組みを八回するうちに八韻(十六句)の詩が出来上がったという才能豊かな人でもあったようです。
外の小説『魚玄機』に詳しく書かれていますが、「鍾馗」さまのような鬚のはえたたくましい顔で、豪放な人物だったようです。歯に衣を着せぬ言動のために科挙も受からなかったそうですが、「八たび手を叉(こまぬ)けば八韻の詩が成るので、温八叉(おんはっさ)と云う渾名」があるそうで、つまり腕組みを八回するうちに八韻(十六句)の詩が出来上がったという才能豊かな人でもあったようです。
森![]() 外の「魚玄機」は、唐詩人を全面に出した小説ですが、詩人の精神を描いて面白い作品ですよ。
外の「魚玄機」は、唐詩人を全面に出した小説ですが、詩人の精神を描いて面白い作品ですよ。
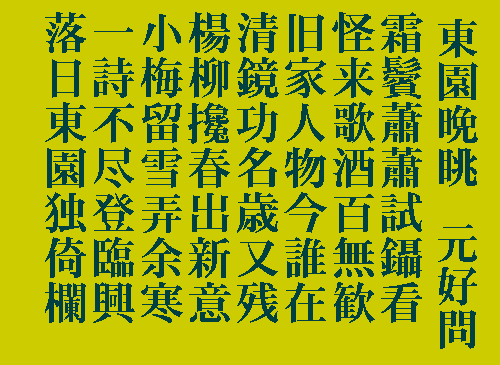
霜鬢蕭蕭試鑷看 霜鬢 蕭蕭として 試みに鑷(ぬきと)りて看る
怪来歌酒百無歓 怪しみ来る 歌酒は百も歓無きを
旧家人物今誰在 旧家の人物 今 誰か在る
清鏡功名歳又残 清鏡 功名 歳又残す
楊柳![]() 春出新意 楊柳は春を
春出新意 楊柳は春を![]() (たす)けて 新意を出し
(たす)けて 新意を出し
小梅留雪弄余寒 小梅は雪を留めて 余寒を弄す
一詩不尽登臨興 一詩は尽くさず 登臨の興
落日東園独倚欄 落日 東園 独り欄に倚(よ)る
<通釈と解説>
3月になると、高校は卒業式を迎えます。暖かな日も多くなるのですが、何故か卒業式の日は冷え込むことが多く、私は体育館で式の間、別れの涙よりも寒さに震えることの方が記憶に残っています。
しかし、暦の上でももう啓蟄、梅の枝にも紅白の花が咲いて、春を感じさせてくれます。
寒さと暖かさの同居するこの時期の詩として、金の元好問の詩『東園晩眺』を読みましょう。
[口語訳]
霜のように白い鬢の毛は寂しく、試しに抜いて眺めてみる
どうしたことか、歌も酒も百に一つも楽しみを与えてくれない。
古い名門の人々は、今誰が健在だろうか
澄んだ鏡に映るのは、かつての功名、老残の日々
柳は春を扶けて新たな趣を見せ、
小枝の梅は雪を載せて余寒をもてあそんでいる
一編の詩で高台に臨んでの感興を語り尽くせず、
落日の中、東園でひとり、欄干に寄りかかるのだ
中華の伝統をひとり受け継ぐべき使命を胸に、モンゴルの支配下での金の国の人々の悲惨な末路を見つめ続けた元好問の憂いの表情が目に浮かぶような詩で、私の好きな詩の一つです。
他民族の侵略によって亡国の憂き目を見た詩人は沢山いますし、その中には、二君に仕えずに死を選んだ人物もいれば、心ならずも征服王朝に仕えることになった人物もいます。彼等の残した詩を私たちは読むと、忠義だの美徳だのという観点で安易に評価することの誤りを感じます。
自分の国が滅ぶ、滅んだということへの痛切な心の叫びが、どちらからも聞こえてきます。「詩を読んでも酒を飲んでも楽しみはない」という第二句や、第七句の「詩でさえも語り尽くせない憂愁」に胸を曇らせる詩人にとっては、春の息吹も決して心を躍らせるものではなかったのでしょう。
空洞化、形骸化した現在の我が国の政治社会の中では、私たちの憂いはどこに向かうのでしょうか。
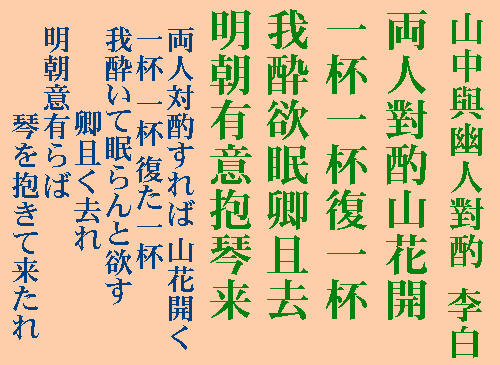
両人對酌山花開 両人対酌すれば 山花開く
一杯一杯復一杯 一杯 一杯 復た一杯
我酔欲眠卿且去 我酔いて眠らんと欲す 卿且(しばら)く去れ
明朝有意抱琴来 明朝 意有らば 琴を抱きて来たれ
<通釈と解説>
昨年の春分の推薦詩は、李白の『春夜洛城聞笛』でしたが、今年はやはり李白で、『山中與幽人對酌』を推薦しましょう。
春寒の日があったかと思えば、一日違いで暖かい春の陽気、この時期は身体を天候に適応させるのも大変ですし、そうそう、花粉で困っていらっしゃる方も多いでしょうね。山の中で「一杯また一杯」と酒を飲み続けていられたら、きっと心身共に頑強になるような気もします。
[口語訳]
二人差し向かいで酒を飲んでいると、丁度、山の花が開いていく。
一杯、まあ一杯、またまた一杯
私はどうやら酔って眠くなったようだ。君はまた、好きにしてくれ。
明日の朝、その気になったら琴を持って来てくれよ。
承句の「一杯一杯復一杯」の、度肝をぬくようなリズム感がこの詩を引き立てていますが、さらには転句の「我酔欲眠卿且去」という姿、私は初めてこの詩を読んだ時には、「何と威張っているのか!」と思いました。
「酔って眠くなったからオレは寝る。お前は去れ」とは、あまりにも失礼な態度ですよね。陶淵明に倣ったとも言われますが、それにしても、豪放、傲慢でしょう。
私はお酒に強くありませんから、宴席でも酔ってくるとすぐに眠くなってしまいます。しかし、家でならともかく、仕事の上での宴会や、卒業生たちとのコンパなどで、勝手に先に寝てしまうというわけにもいきませんから、眠気と闘うこともよくありました。そんな時、この詩を思い出しては、李白をうらやましく思ったものです。
最近は、李白のこの詩も、そんなに威張ったものではないと読めるようになりましたが、でも、それでもこんな風に言ってみたいという気持ちになることはありますよね。
今回の感想は、あまり春分とは関係がなくなってしまいました。本来の目的は、起句の「山花開」で書こうと思っていたのですが、ま、こんなところで良しとしていただきましょうか。